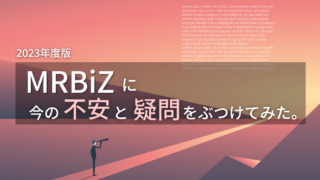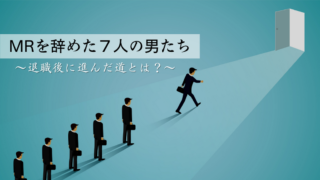【※この記事は読書MEMOです】
「20歳の自分に受けさせたい文章講義」古賀史健
【率直な感想】
「話せるのに、なぜ、書けないのか?」の理由がこの本のおかげで解明した。そして、「どうやったら書けるか?」を”技術”としてマスター出来る。「文才がない…」なんて、ただの言い訳だった。
※ハイライトした箇所を、読書MEMOとして、一部抜粋しています。
まえがき「話せるのに書けないのはなぜか?」

文章の苦手な人が悩んでいるのは「話せるのに書けない!」というもどかしさなのだ。誰だって話すことはできる。感情にまかせて口喧嘩することも、気のおけない仲間たちと夜通し語り合うことだって出来る。にも関わらず、メールの一通すら「書けない!」のだ。
ここではっきりさせておこう。
「話すこと」と「書くこと」は、まったくべつの行為だ。
言葉を話す時、あなたは”テレビ”である。
満面の笑みを見せることもできるし、怒鳴り声を上げることもできる。自分の気持を言葉、表情、声、身振りなど、さまざまな道具を使って伝えることが出来る。
一方、文章を書くときのあなたは”新聞”である。
喜怒哀楽を表情で伝えることもできないし、怒りに震える声を聞かせることもできない。テレビどころか”ラジオ”ですらないのだ。使える道具は、言葉(文字)だけ。声や表情などの使い慣れた武器をっすべて奪われ、ただ言葉という棒きれ一本で勝負しろと迫られる。
なぜ、若いうちに”書く技術”を身につけるべきか?
答えはひとつ「書くことは、考えること」だからである。“書く技術”を身につけることは、そのまま”考える技術”を身につけることにつながるからである。
われわれの頭のなかには、たくさんの”思い”が駆けめぐっている。もちろん”思い”は目に見えない。言葉であるとも限らない。
不鮮明な映像であったり、色だったり、あるいは漠ぜんとした気配や予感のようなものかもしれない。
“思い”というと言語化されたもののようだが、頭をぐるぐると駆けめぐっているのは言葉ではない。言葉以前の、茫漠たる”感じ”である。このぼんやりした”感じ”や”思い”のこと、そしてそれが駆けめぐるさまのことを、ぼくは「ぐるぐる」と呼んでいる。
話すのであれば、「ぐるぐる」の”感じ”を喜怒哀楽の声や表情で伝えることもできる。しかし文章では声が出せず、表情も見せることができない。
じゃあ、どうすれば文章が書けるか?
ぼくの結論はシンプルだ。書くことをやめて“翻訳”するのである。文章とは、つらつらと書くものではない。頭の中の「ぐるぐる」を、伝わる言葉に”翻訳”したものが文章なのである。
①文章を書こうとすると、固まってしまう。
②自分の気持をうまく文章にすることができない。①で悩んでいる人は、まだ頭のなかの「ぐるぐる」を整理できていない状態だ。
文章とは頭のなかの「ぐるぐる」を”翻訳”したものだ、という発想が欠如している。まず必要なのは”翻訳”の意識付けだろう②で悩んでいる人は、「ぐるぐる」を”誤訳”してしまっているわけだ。こちらはもっと具体的な”翻訳”の技術が必要だろう。
われわれは、自分という人間の”翻訳者”になってこそ、そして言いたいことの”翻訳者”になってこそ、ようやく万人に伝わる文章を書くことができる。
われわれは「書く」という再構築とアウトプットの作業を通じて、ようやく自分なりの「解」を掴んでいくのだ。
順番を間違えないようにしよう。
人は解を得るために書くのだし、解がわからないから書くのだ。
文章の世界では、しばしば「考えてから書きなさい」というアドバイスが語られる。もしも目の前に20歳の自分がいたら、ぼくはもっと根本的なアドバイスをおくるだろう。
つまり「考えるために書きなさい」と。
書くことは考えることであり、「書く力」を身につけることは「考える力」を身につけることなのだ。”書く”というアウトプット作業は、思考のメソッドなのである。
文章は「リズム」で決まる
論理破綻に気づくためのキーワードは「接続詞」だと、ぼくは思っている。ライターの世界では「接続詞を多用するな」とアドバイスされることが多い。
だが、断言しよう。みんなもっと接続詞を使うべきだ。
情報を伝えるために必要なのは、美しさではなく正しさである。美しさとは、どこまでも主観的なモノサシである。一方、正しさを意識することは、客観的な目線を意識することにつながる。
ぼくはいかなる種類の文章も”正解”が存在するとは思わない。しかし同時に、あからさまな”不正解”は存在すると思っている。
われわれにとっての「伝えるべきこと」、それは第一に”自分の意見”だ。
“自分の意見”こそ、最大の「伝えるべきこと」である。そして大切なのは、”自分の意見”が完全な主観であり、感情だということだ。文章という声も表情もないツールを使うかぎり、その”感情”は論理のレールに乗せてやらないと届かない。われわれは”感情”を伝えたいからこそ、論理を使うのだ。“主観”を語るからこそ、客観を保つのだ。
文章にリズムを持たせるには、もうひとつシンプルな方法がある。断定だ。言い切ってしまうことだ。
しかし、断定のことはその切れ味の鋭さゆえのリスクが伴う。断定の言葉は、あまりに強すぎるのだ。
それでは、どうすれば断定という刃を使うことができるのか?やはり論理なのだ。断定する箇所の前後を、しっかりとした論理で固めるしかないのである。
個人的にぼくは、みんな批判を恐れずもっと断定すべきだと思っている。これは文章もそうだし、日常会話でもそうだ。断定するには、相当な自信が必要だと思われるかもしれないが、ぼくの考えは逆だ。
自信があるから断定するのではなく、自信を持つために断定する、というアプローチを考えてもいいのではないか。
読者は説得力のある言葉を求めており、言葉の説得力は「断定というリスク」を冒してこそ生まれるのだ。
構成は「眼」で考える
文体の妙、文章の個性、あるいは文章の面白さ。これらを決めているのは、ひとえに構成である。論理展開である。
日常文だからこそ大切になる要素がある。それは、導入部分の書き方だ。最初の数行を読んでつまらないと思ったら、もう読んでもらえない。読者はいつも「読まない」という最強のカードを手に、文章と対峙しているのである。
となれば、導入の目的はひとつしかないだろう。
読者を劇場へと誘導し、まずは”椅子”に座ってもらうことだ。
論理的であるとは、すなわち「論が理にかなっている」ということだ。ここでの「論」とは”主張”のことだと考えればよい。そして「理」は”理由”と考える。つまり、自らの主張がたしかな理由によって裏打ちされたとき、その文章は「論理的」だと言えるのだ。
ここで考えなければならないのは「なぜ伝えるのか?」という自らへの問いかけである。どうして文章などというまどろっこしい手段を用いて、多大な時間と労力を費やして、自分は書いているのか。理由はただひとつ、読者を動かすためだ。
自分が有益だと思った情報を伝えることで、他者の心を動かし、ひいては行動まで動かす。文章を書くことは、他社を動かさんとする”力の行使”なのである。反発が恐ろしいくらいなら、文章など書かないことだ。
自分の文章のなかに、主張、理由、事実、の3つがあるか、そしてその3つはしっかりと連動しているか、いつも意識するようにしよう。
文章は”面倒くさい細部”を描いていこそ、リアリティを獲得する。そして”面倒くさい細部”の描写によって得られたリアリティは、読者の理解を促し、文章の説得力を強化するのだ。
読者の「椅子」に座る
アマチュアだろうとプロだろうと、メールだろうと小説だろうと、あらゆる文章の先にはそれを読む”読者”がいるのだ。文章は文章であるかぎり、そこにはかならず読者が存在するのである。必要なのは、隣に立つことだけではなく、読者と同じ椅子に「座ること」である。
結局、われわれが本当の意味でその「椅子」に座れる読者は、世の中に2人しかいない。①10年前の自分 ②特定の”あの人”
有益な情報とは、往々にして「もしこれを10年前に知っていたら!!」と思わせるものである。
10年前に知っていたら、自分の人生は変わったかもしれない。10年前に知ったいたら、あんな苦しい思いをせずにすんだかもしれない。あんなに悩まずにすんだかもしれない。もしそんな思いがあるとしたら「10年前の自分」の椅子に座ればいい。「10年前の自分」に語りかけるようにして書けばいいのだ。
彼や彼女がどんな景色を見て、どんな悩みを抱いているのか。どんな言葉を嫌い、どんな言葉に耳を傾け、どう伝えれば納得してくれるのか。すべてが手に取るようにわかるはずだ。こうして書かれた文章は言葉の強度が違う。
人間は、どんな時代も同じこと(普遍的なこと)をことを考え、同じことに悩み、同じことで苦しんでいる。自分だけにしか分からない、誰にも理解されないと思われる根深い問題こそ、じつは普遍性を持った悩みなのだ。
なぜあなたは10年前の自分にむけて書くべきなのか?いま、この瞬間にも日本のどこかに「10年前のあなた」がいるからだ。
文章にかぎらず、宣伝や商品開発など、さまざまな企画段階で思い悩んでいる方には、ぜひ「あのときの自分」を思い起こしていただきたい。「あのときの自分」の椅子に座ることとは、昔を懐かしむことでも、独りよがりになることでもない。いまを生きている「見知らぬ誰か」の椅子に座る、いちばん確実な方法なのである。
じつは「多数派」を対象とするよりも「少数派」に狙いを定めたほうが、誌面づくりはスムーズに運ぶのである。見えやすそうでいて、もっとも顔が見えにくいのが「多数派」なのである。
アルファブロガーと呼ばれる方々のブログをしっかり読み返して欲しい。彼ら・彼女らは、批判も辞さない覚悟で自分の”主張”を述べているはずだ。中途半端に八方美人であろうとしている人なんて、ひとりもいない。強い”主張”があるからこそ読者がついてくるのである。
狙いを定めて言葉のベクトルがはっきるするため、「その他の人々」にも届きやすくなるからだ。多数派をターゲットとすることをやめ、読者を絞り込むこと、特定の”あの人”にまで絞り込むことに躊躇する必要はない。むしろ、”みんな”から喜ばれようとするほど、誰からも喜ばれない文章になるのだ。
専門性に溺れていくと、文章はどんどん雑になる。往々にして、”遠景”を描かず、いきなり対象にクローズアップする。「ここは書かなくてもわかってくれるだろう」「いきなりこの言葉を出しても大丈夫だろう」「これは説明するまでもないだろう」と読者の予備知識に甘え、説明すべきところを説明しようとしない。むしろ「それを書くのは野暮なこと」とまで考えしまうところがある。
専門書やマニア向けの雑誌などが(一般読者にとって)読みづらいのは、このためだ。出てくる言葉が難しいのではない。読者に甘え、本来やるべき説明を怠っているから、読みづらいのである。
もともとひとつの本は、内容で読むひとを限ってしまうところがある。これはどんなにいいまわしを易しくしてもつきまとってくる。また一方で、著者の理解がふかければふかいほど、わかりやすい表現でどんな高度な内容も語れるはずである。これには限度があるとはおもえない。(共同幻想論:吉本隆明)
早い話が「こんな文章で、うちのオカンは理解してくれるかな?」と考えるわけだ。
しかし、少しでも理解のパーセンテージを上げていくようなブラッシュアップする努力を怠ってはいけない。それが「話し言葉から書き言葉へ」につながっていく。難解な文章が”賢い人の文章”だというのは、大きな間違いだ。難解な文章とは、読者の読解力に甘えた、内輪向けの文章にすぎない。あらゆる人に開かれた”平易な文章”ほど難しいものはないのである。
「集中して書いたもの」がそのまま「集中して読んでもらえる」と思っているなら、それは大きな間違いだ。「ながら読み」がほとんどではないだろうか?しかし、ぼくはいかなる読み落としや誤読も、最終的には書き手の責任だと思っている。伝わるように書いてこそ、文章としての機能を果たすのだ。
文章を書き、それを他者の目に触れる場に好評しているということは、心のどこかに「自分のことをわかってほしい」との思いがあるはずだ。「自分のことをわかってほしい」と願うことこそ、それは他社の心の変容を求めていることに他ならない。
ラブレターの目的は、「感動させること」ではない。「自分の告白を受け入れてくれること」であり、文字通り、「口説く」わけだ。つまり、文章の肝は”説得”なのである。しかし、上から押さえつけるような説得に読者は、押したら押しただけ、反発する。もうひとつ道がある。読者を”説得”するのではなく、”納得”させる、という手法だ。
①:説得…押しのアプローチ(読者を押しきる)
②:納得…引きのアプローチ(読者に歩み寄ってもらう)
携帯メールを使わないおじいさんへ向けて、「パソコンは情報社会において必須の知識です」「パソコンを覚えないと時代に取り残されてしまいますよ」これは典型的な「押しのあアプローチ」であり、”説得”である。
一方、「引きのアプローチ」ではこう語りかける。「パソコンを覚えると、お孫さんと毎日テレビ電話でお話することができますよ」孫という最大の関心事を持ち出し、自らパソコンのほうへと歩み寄ってもらうのだ。
おじいさんパソコンという、本来なんの接点もない両者を「孫」のひと言によって関連付けるのである。
人は「他人事」では動かない。読者が”説得”に応じようとしない理由は簡単である。基本的にわれわれは、他人事には興味がないのだ。
われわれは「正しい」だけでは動けないのだ。頭で「正しい意見だ」と理解できても、肝心の”心”が動かないのである。一般論を述べるばかりの文章が心に響かない理由は、ここにある。主張のどこかに「これは他人事じゃない!」と思わせる要素が含まれていないと、われわれの心は動かない。当事者意識を芽生えさせ、他人事を「自分事」に変換してくれる、なんらかの仕掛けが必要なのである。「関連づけ」は、そのわかりやすい一歩だろう。
文中の早い段階で、独自の”仮説”を提示する。一般論とは、相反するような”仮説”だ。そして読者に「あなたはこの仮説をどう思うか?」っと問いかけ、読者と一緒になって、その”仮説”が正しいかどうかの検証作業にあたるのである。
小説などのフィクションでは、物語のなかに読者を巻き込み、読者は登場人物に感情移入することもあるし、起伏に富んだストーリーをそのものに見を委ねることもある。
一方、物語性に乏しいノンフィクションや実務系の文章では、どうしても独演会形式の、一方通行な内容になりがちだ。そして多くの場合、読者は不本意な「知識の球拾い」を強いられることになる。
しかし、ここに”仮説”が入ると、自体はガラッと変貌する。”仮説と検証”の作業には、どこかミステリー的な要素が含まれていないだろうか?
むしろ一般論が否定されることによって「どんな議論が展開されるんだ?」と興味を引くことができる。
しかし、あらゆる”主張”は仮説なのである。
極端なことを言ってしまえば、「人を殺してはいけない」も仮説だし、「ものを盗んではいけない」も仮説だ。
問題は、仮説を自分ひとりで片づけてしまうのか、それとも読者に問いかけ、一緒に検証していくのか、という点にある。
文章の「起”転”承結」を成立させるためには、冒頭に「自らの主張と真逆の一般論」を持ってくる必要がある。
あなたが、「インターネットは素晴らしい!」と主張したいのなら、冒頭には「インターネットは恐ろしいものだと言われている」という真逆の一般論をもってこなければならない。
「文章は冒頭が難しい」とはよく言われる話だ。たしかに「起”転”承結」の構成でもっとも難しく、もっとも神経をつかうべきは、”起”の部分なのである。
読者の椅子に座るときは、次の言葉を頭に入れておこう。「すべての読者は”素人”である」あなたの”主張”を正確な形で知っているのはあなただけであり、すべての読者は「それを知らない素人」なのである。だから、われわれは文章を書くとき、常に「自分は(そのテーマについて)なにも知らない”素人”に向けて書いている」ことを意識しなければならない。
自分が「なにも知らない素人」だったときを思い出し、そこからどうやって「一本道」を見つけていったのかを考える。どんな回り道をして、どんな行き止まりにぶつかったのかを詳細に思い出す。そして読者とともに、文章のなかでもう一度「ムダな回り道」を歩くのだ。
「いかがでしたでしょうか?」
後半になるにつれ、どんどん話がまどろっこしくなっていますが、ぼくは、以下の”2つ”の話を聞いて、書くことに対するモヤモヤが晴れた気がします。
・「話すこと」と「書くこと」は、まったくべつの行為だ。
・「考えるために書きなさい」
※MEMOは、まだ途中なので、完成したらまたインスタで流します。
ちなみに、
「Airpods持っているから耳で聴きたい!」という方は、Amazonの聞く読書、Audibleだと無料で聴けます。
※12/26(月)まで、「2か月間の無料体験」および100ポイント分のAmazonポイントがもらえるキャンペーンが行われており、お得な期間のようです。ご興味ある方はどうぞ。>>【無料】Amazonオーディブルで本を1冊もらう方法【3STEP】